本校では、車いすを使用している児童・生徒が多数在籍しています。
車いすに関して、その種類としくみを、以下のホームページより、許可を得て転載しています。
転載元 とうきょう福祉ナビゲーション
http://www.fukunavi.or.jp/fukunavi/kiki/wheelchair/chair_01.html
車いすは、大きく分けて手動のものと、電動のものに大きく分かれます。
ここでは、手動の車いすについてお話します。手動車いすとは、人の力を利用して動かす車いすのことです。手動の車いすには自走用と介助用のものがあります。
自走用車いすは、利用者本人が腕の力などを利用して、車いすを走行するもので、介助用車いすは、介助者が後方から押すことで車いすを動かすものです。
一般的な自走用車いすの構造および各部の名称を図1に示します。
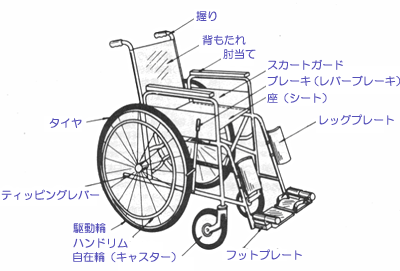
図1 車椅子の各部の名称
いすとして体を支える部分には、以下のものがあります。
座(シート)
背もたれ
肘あて
フットプレート(足底を乗せます)
レッグプレート(ふくらはぎを支え足部がフットプレートから後ろに落ちることを防ぎます)
スカートガード(衣服がタイヤに巻き込まれることを防ぎます)
車いすが走行する部分は、以下のものがあります。
駆動輪(移動するときに駆動力を伝える車輪です)
自在輪(キャスター、前輪)
ブレーキ(乗り降りの際にタイヤが動かないようにロックします)
駆動輪はさらにタイヤとハンドリム(手でこぐときに持つところ)から構成されます。タイヤの直径は22インチのものが多く、24インチ、20インチのものもあります。介助用車いすはこの駆動輪が16インチと小さく、ハンドリムはついていません。一般に車輪の直径が大きいほうが乗り心地がよく、段差を乗り越えやすいです。
介助するための部分には、以下のものがあります。
握り(介助者が操作するときに使います)
ティッピングレバー(段差などで自在輪(キャスター)を上げるときに、介助者が足で押さえます )
 東京都立小平特別支援学校
東京都立小平特別支援学校